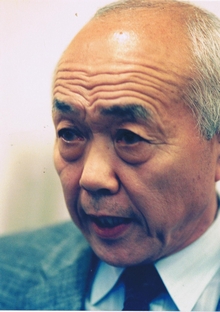東京大空襲
1945年3月10日。私は9才。小学4年。父と疎開先の伊豆韮山村から、4-5日の予定で上京していた。滞在先は、東京の大田区、休業中の蒲田の店だった。
お昼過ぎ。ラジオから大本営の空襲警報発令。遙か1万メートルの上空に無数のB29大型 爆撃機が出現し、編隊を組んで東京全域を爆撃し始めた。大本営や軍隊がある場所、主要な地域は爆弾投下。市街地、住宅街は焼夷弾が雨のように投下された。町は見る見る内に大火災。あたりは火の海と化していった。地元の人々は防空壕など普段訓練していた避難所に逃げ隠れた。
しかし父とはぐれた私は逃げ場が無かった。ただ本能的に町中を無我夢中で逃げ走り、やっとのことで、仲蒲田から玉川の下流、六郷川原に辿りついた。衣類は泥で汚れ、ぼろぼろ。身体が熱くて玉川に飛び込んだ。あの時の川の水は気持ちがよかった。「助かった」と自分一人で感動したものだ。
その後、玉川の堤防伝いに丸子橋、二子橋を越えて、川崎市久地の祖父母の家に着いた。深夜だったと思う。逃げるだけで無我夢中だったから、疲れは覚えなかった。幸い玉川の堤防はほぼ直線で、夜道も迷わない。やっと祖父母の家に辿りつき、力が抜けて動けなくなった。なにしろ10時間以上逃げまわったから、子どもにしてもかなりの距離だった。
思えば、韮山の開墾に3里(12km)の山道を歩いていた。牛車を牽きながら、熱海峠近くまで毎日通った。その辛さが、逃げる時の気力と体力を養ってくれた。
次の日。蒲田に戻った。途中は一面全焼。東京は見渡すかぎりの焼け野原だ。我が家の店など何処にあったか見当もつかない。何しろB29大型重爆撃機が600機、計画的に絨毯爆撃というから、どうしようもないわけだ。東京は焼け野原となった。死者もかなりいた。しかも防空壕の避難でかなり死んだ。かぶせた土砂の重みで潰れ、生き埋めになったという。私の親戚の家族も防空壕で死んだ。避難して命を落とすとは気の毒だった。
お昼過ぎ。ラジオから大本営の空襲警報発令。遙か1万メートルの上空に無数のB29大型 爆撃機が出現し、編隊を組んで東京全域を爆撃し始めた。大本営や軍隊がある場所、主要な地域は爆弾投下。市街地、住宅街は焼夷弾が雨のように投下された。町は見る見る内に大火災。あたりは火の海と化していった。地元の人々は防空壕など普段訓練していた避難所に逃げ隠れた。
しかし父とはぐれた私は逃げ場が無かった。ただ本能的に町中を無我夢中で逃げ走り、やっとのことで、仲蒲田から玉川の下流、六郷川原に辿りついた。衣類は泥で汚れ、ぼろぼろ。身体が熱くて玉川に飛び込んだ。あの時の川の水は気持ちがよかった。「助かった」と自分一人で感動したものだ。
その後、玉川の堤防伝いに丸子橋、二子橋を越えて、川崎市久地の祖父母の家に着いた。深夜だったと思う。逃げるだけで無我夢中だったから、疲れは覚えなかった。幸い玉川の堤防はほぼ直線で、夜道も迷わない。やっと祖父母の家に辿りつき、力が抜けて動けなくなった。なにしろ10時間以上逃げまわったから、子どもにしてもかなりの距離だった。
思えば、韮山の開墾に3里(12km)の山道を歩いていた。牛車を牽きながら、熱海峠近くまで毎日通った。その辛さが、逃げる時の気力と体力を養ってくれた。
次の日。蒲田に戻った。途中は一面全焼。東京は見渡すかぎりの焼け野原だ。我が家の店など何処にあったか見当もつかない。何しろB29大型重爆撃機が600機、計画的に絨毯爆撃というから、どうしようもないわけだ。東京は焼け野原となった。死者もかなりいた。しかも防空壕の避難でかなり死んだ。かぶせた土砂の重みで潰れ、生き埋めになったという。私の親戚の家族も防空壕で死んだ。避難して命を落とすとは気の毒だった。